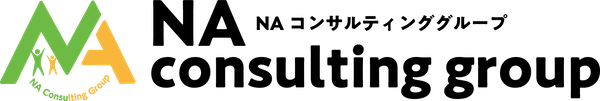2025年07月16日
【第4回】年金について知っておきたいこと~老後だけじゃない、年金制度の役割~

こんにちは、新潟にあるNAコンサルティンググループ・社労士のSです。
このコラムでは、「労働保険」や「社会保険」について、全6回でわかりやすさ重視でお届けします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
年金と聞くと、「老後にもらうもの」というイメージを持っている方が多いと思います。
たしかに、老後の生活を支える「老齢年金」は年金制度の中心的な役割です。
でも実は、それだけではありません。
日本の公的年金制度には、老齢年金のほかに「障害年金」や「遺族年金」も含まれており、人生の様々な場面を支える役割があります。
今回は、3つの年金の基本をわかりやすくご紹介します。
➀【老齢年金】 老後の生活を支える
◆老齢年金は、原則として65歳から受け取ることができる年金です。
支給を受けるには、原則10年以上の保険料を納めた期間が必要です。
◆老齢年金には、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」があります。
自営業の方などが加入するのが国民年金、会社員や公務員などが加入するのが厚生年金です。
厚生年金に加入している人は、国民年金に上乗せする形で老齢年金を受け取ることができます。
◆「繰り上げ受給」または「繰り下げ受給」といって、65歳ではなく60歳から早めに受け取ったり、または75歳まで待って受け取ることも可能です。
その場合は、繰り上げて早めに受け取ると年金額が減り、逆に繰り下げて遅らせると年金額が増える、という仕組みになっています。
②【障害年金】 病気やけがで日常生活がつらくなったときを支える
◆障害年金は、病気やけがで生活や仕事が困難になったときに支給される年金です。
一定の障害状態にある方が対象で、障害年金に対しては税金がかかりません。
◆たとえば、うつ病や糖尿病、がんなどでも、状態によっては障害年金の対象となることがあります。働きながら障害年金をもらうこともできます。
◆申請には、初診日や障害の程度を示す診断書などが必要になりますが、「自分は該当しないだろう」と思っていた方が実は対象だった、というケースも多いです。
③【遺族年金】 大切な人を亡くした家族を支える
◆遺族年金は、生計を支えていた人が亡くなった場合に、その家族(配偶者や子どもなど)に支給される年金です。
たとえば会社員だった夫が亡くなった場合、妻や子どもが遺族年金を受け取ることができます。遺族年金も税金がかかりません。
◆生活をともにしていた家族が亡くなるのは、精神的にも経済的にも大きなダメージです。
遺族年金は、残された家族の生活を守る大切な制度となっています。
まとめ
年金制度は「老後のためのもの」と思われがちですが、実は人生のさまざまなリスクに備える「生活保障」の制度でもあります。
将来のための老齢年金に「障害特約」「遺族特約」をセットしても、社会保険料が上がることはありません。
【老齢】・【障害】・【遺族】の3つの柱によって私と家族の暮らしを支えている、とても頼りになる制度です。