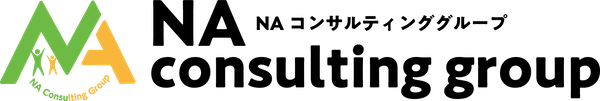2025年05月21日
【第3回】「扶養」って2種類あるって知ってましたか?

こんにちは、新潟にあるNAコンサルティンググループ・社労士のSです。
このコラムでは、「労働保険」や「社会保険」について、全6回でわかりやすさ重視でお届けします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「扶養の範囲で働きたいんです」──パートやアルバイトの方から、よく耳にする言葉です。
実は、「扶養」には税金に関する扶養と健康保険に関する扶養の2種類があるのをご存じでしょうか?
今回は、この2つの扶養の違いから、扶養を外れることで得られるメリットまで、わかりやすくご紹介します。
➀「扶養の範囲」とは?
■ 税金に関する扶養(=税金の計算に関わります)
○収入の基準
・年収103万円以下(給与の場合)
○扶養する人のメリット
・配偶者控除や扶養控除で税金が安くなる
○扶養される人のメリット
・税金がかからない
■ 健康保険に関する扶養(=社会保険の手続きで使用します)
○収入の基準
・年収130万円未満(60歳以上または障害者の方は180万円未満)
○扶養する人のメリット
・基本的にはなし(健康保険料は被扶養者の数に左右されない)
○扶養される人のメリット
・健康保険料を支払わなくてよい
・国民年金の保険料が免除される(60歳未満の配偶者の場合)
・被扶養者として医療サービスを受けられる
②扶養の範囲(=「収入の壁」)を超えると?
■ 103万円の壁(税法上)
・年収が103万円を超えると、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなり、扶養する人の税金が増える可能性があります。
■ 130万円の壁(健康保険) ※60歳以上または障害者は180万円
・年収が130万円を超えると、健康保険の扶養から外れ、自分で健康保険料を負担する必要があります。
・加入先は、①勤務先の社会保険(健康保険+厚生年金)、または②国民健康保険+国民年金、どちらかになります。
③扶養を外れるメリットは?
単に「扶養内=お得」とは限りません。
扶養を外れることで、こんなメリットもあります。
①社会保険の給付を受けられる
傷病手当金や出産手当金など、病気・ケガ・出産をしたときに保険給付が受けられるため、生活の保障が充実します。
②厚生年金に加入できる
将来の年金額が増えるので、老後の生活の安定につながります。
③収入の上限がなくなる
扶養の制限を気にせず働く時間を増やせるため、収入アップが見込めます。
まとめ どちらが自分に合っていますか?
「扶養内で働く」か、「扶養を外れる」かは、あなたのライフスタイルや将来設計次第です。
短期的な節税か、長期的な保障か・・・それぞれのメリット・デメリットを理解して、納得のいく働き方を選んでいただきたいと思います。